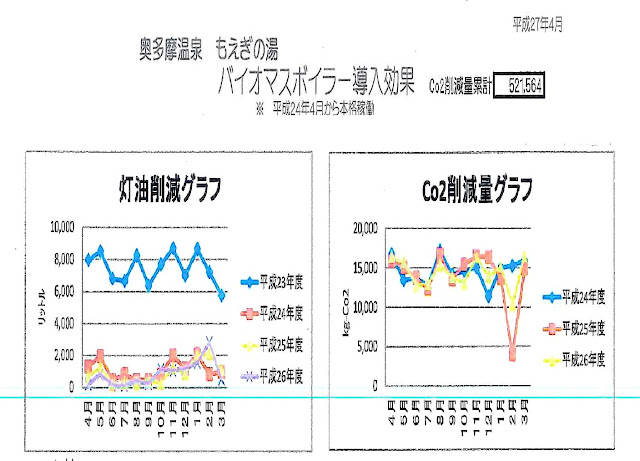「関東・山梨ブロック林業グループコンクール」レポ-ト
(H27.7.9神奈川県足柄上郡大井町・いこいの村あしがら)
会員 栖島
青梅りんけんより3名:高田・中島(大)・楢島 で参加してきましたので報告致します。
全国林業研究グループ・田爪会長のあいさつから
九州の林業に関して、今後外材が入って来なくなることを見越し、これまでの銘木を目指した山つくりから短期伐採での再生産を重視した林業に切り替えが大切である、と話されていました。
次に関東・山梨ブッロクから8団体の発表がありました。
発表内容要約
1)東京:八王子市林業研究会
恩方第二小学校での5・6年生を対象に間伐作業の体験教室を開催。9年前から都内唯
一の滝山道の駅で木工クラフトや巣箱つくり、丸太切りの体験を行っている。会員と
小学生や市民と山の話題での交流により森林についての対話を増やしている。
2)山梨:ますほ里山暮らしを学ぶ会
プロでなくても出来る森林整備、間伐材の利用、暮らしを見直すきっかけ作り、と言う視点で活動している。簡単な道具でできる「皮むき間伐」を行い、間伐材で自転車スタンドつくり温泉施設や道の駅に設置。薪を使って焼く「登り窯」陶器つくり。町田市の道の駅にベンチと掲示板を設置し交流が広がっている。
3)埼玉:西川林業クラブ
20年以上にわたり小中学校への林業教育としてスライドを用いた授業と林業体験の取り組み。西川材のPRとして西川材フェアーを参画し木工工作コンクールで触れ合う機会を増やしている。会員意欲向上のためH23/24年に四万十式作業路解説研修を講師を招いたり、H25にはGPS測量研修を行う。安全教育のために子供用ヘルメットを70個用意、移動してしまう学校の先生とは粘り強い交流が大切である、と力説してる。
4)栃木:日光地区木材流通研究会
メンバー8名だが各組織のトップの方が集まったことにより、多岐にわたった高い専門性をもった活動をしている。宇都宮大学との共同研究、専門学校・高校とのインターシップ研修、森林認証の導入、冊子による地産地消のPR活動。
特に認証制度の普及により原料から最終消費者までの流通トレーサビリティーを確立し「顔の見える木材での家づくり」を行うなど、一企業並みの活動をしている。
5)群馬:三国林業研究会
水上町道の駅のナメコ販売は震災後にほぼゼロとなり、ナメコ原木の放射性物質減少への試みとして試験研究を行う。原木・ほだ木・きのこ、で除染を行いセシウム濃度の変化を測定。低減処理方法を4区に分けて顔料を使用するなど、かなり専門的に高精度な試験を行っている。効果は確認できたが汚染は原木まで及んでおり、ナメコ販売の復活には長い時間と支援が必要であること、を訴えていた。
6)茨城:山方林業研究会
林業以外の副収入として原木マイタケ栽培を行いその普及に取り組む。H11から山方町の助成を受け常圧殺菌窯による原木殺菌をし、培養したほだ木を販売して伏せ込み方法や管理の指導まで行う。また、炭焼き技術の伝承と町のBBQ施設への提供のため、助成を受けてH12より炭焼きを始める。震災による窯のひび割れも修復し昨年は8回の製炭で2トンを生産、今後は市民への技術の伝承を行って行きたい。
7)千葉:千葉県林業研究会千葉支部
山武杉の非赤枯性溝腐病になった被害林の伐採・再造林が活動の柱。共同作業ではあるが森林所有者が16,000円の日当を払うことで仕事としての意識を持ち責任感が生まれ、継続的にできる要因になっている。作業効率確認で、バックホウ2台・伐り手4人で5日間1haを行えることが分かり、千葉市内の59%の被害林が再生された。今後も会員の負担にならない範囲で森林整備を行って行きたい。
8)神奈川:南足柄市森林ボランティア協議会
2haほどのモデル林の手入れ作業と森林教育体験の開催が主な活動。森林体験では、きのこ観察会として採取からキノコ汁うどんつくりを行う。ほだ木つくりでは伐採から植菌を行う。会員の平均年齢70歳以上なので活動時の安全を第一にし、今後は若返りをを進めたい。会費は取らず間伐材を売った収入などで活動していると言う事でした。

審査結果と感想
一位になった日光地区木材流通研究会は断トツの内容の濃さで、8名の活動内容とは思えませんでした。二位の三国林業研究会はキノコおたく的な突き詰めた研究内容で、正直良く理解できませんでしたが、質疑での数値を交えた回答はさすがでした。
個人的には山梨ますほ里山暮らしを学ぶ会、の全く林業経験者のいない主婦が主なメ
ンバーで活動されているという異色さと、決して大きくない活動ですが着実に実行に
移しているところが印象に残りました。
追伸;質疑で紹介された樹種「コウヨウザン」・・・成長が早く萌芽する木としての特徴が注目されています。